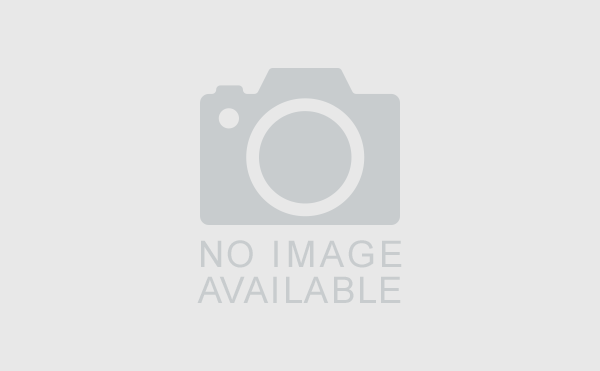磁場の距離減衰について
大雑把なイメージとして、起磁力を大きな磁石に例えれば、距離減衰の仕方は、その長さ(磁気モーメントの長さ)に依存します。
磁気モーメントが長いと、距離減衰は緩やかに、短いと急激になります。
磁気モーメントは、N極とS極の2つの磁荷面(磁石の太さあり)です。
下図は地磁気をイメージしたときの図です
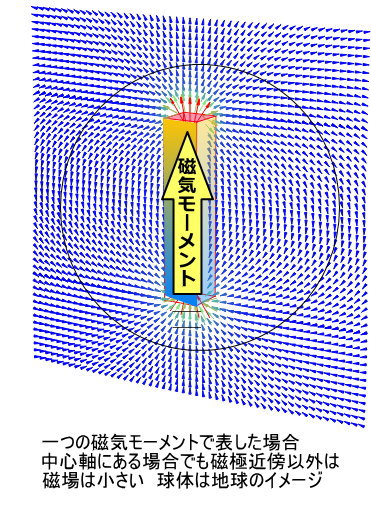
もう少し正確に電流といった形で、表現する場合は、円電流を束ねたコイルをイメージになります。
もちろん、これらは、あくまで全てイメージとして考える場合で、Qmは、厚みのある立体的なコイルを(離散化された)立体電流で計算しています。
上記を数式として定量的に表現すれば
電場磁場の距離減衰については、その源の形状に大きく依存します。
(1)点源については、クーロンの法則で知られていますように、距離の逆二乗に比例します
\[H=C\dfrac{m}{r^2}\]
\(H:磁場 m:磁荷 r:距離 C:比例定数\)
(2)無限長線源については、アンペールの法則が示すように距離に反比例します。
\[H=C\dfrac{ρ}{r}\]
ρ:線磁荷密度
アンペールの法則は電流ですが次のようになります。
\[H=\dfrac{I}{2πr}\]
I:電流
(3)無限に広い平板であれば、距離減衰はありません。
\[H=Cσ\]
\(σ:面磁荷密度\)
(4)有限長の線源の場合は、ビオサバールの法則があり、線源を見る角度のファクターが入り(1)と(2)の中間となります。
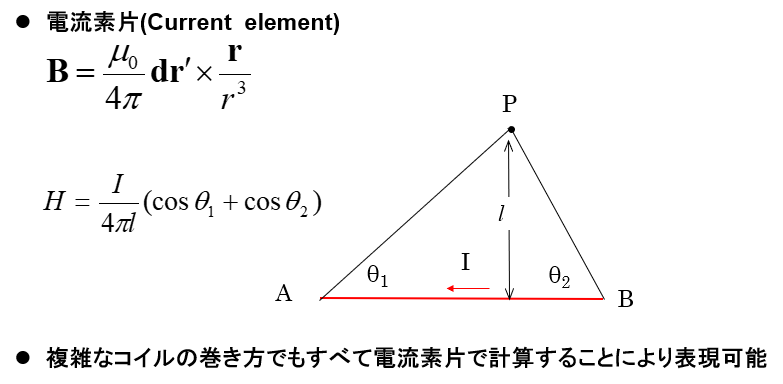
(5)曲面Sが源であると積分にした形になります。 面磁荷密度が一定の場合、(2)と(3)の間で立体角Ωに比例します。
\[H=CΩ\]
\[Ω=\iint_s \dfrac{dS(r ,n)}{r^3}dr\]
なお、Qm の場合、電流関係は、(4)の応用で計算できますが、一般の強磁性体の場合は(5)の解析解(細かく分割して計算する数値解ではなく理論解)を使用しています。
これらはすべて3次元空間上における保存則からくるもので、純粋に幾何学(数学)になります。